医の自給自足
操体法-4
操体法の基本運動
以下の基本運動の6つの動きは、体の基本的な動きを網羅しています。順番は自分のやりたいように、また、2つ3つ選んでもいいです。朝でも夜でも続けていくと、体がしなやかになっていきます。*決して苦しくなる動きはしないよう、引きつりや痛み、嫌な感覚を感じる手前で動きを止めましょう。
基本運動その1
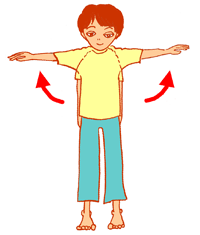
- (1)足は腰の幅ほどに開き、つま先は平行にして、前を向き、背骨は自然に伸ばして、楽に立ちます。←基本姿勢。
- (2)息を吐きながら、両腕をゆっくりと水平に上げていきます。
- (3)両腕が水平になったら、そのまま一呼吸して、呼気でバサッと落とします。
- (4)(1)~(3)を3~5回繰り返します。
- (5)もし、一方の腕が上げにくいと感じたら、上げにくい側の足に重心をかけると、両腕が同じように上がります。左図は右腕が水平になっていないため、右足に重心をかけます。
基本運動その2

- (1)基本姿勢でやや顎を引き、ひざが直角になる位にももを上げ、足裏が床に平らに着くように、力強くドンドンと足踏みをします。
- (2)このとき腕は、肩の高さ程に大きくふり上げます。30~50回。
- (3)もうひとつの方法は、呼気3回+吸気1回の4拍子での足踏みです。呼気3回+吸気1回で、足踏み4回(歩)になります。
- (4)上がりやすい側のももは、より高く、踏みつけやすい側の足は、より強く踏みつけてみましょう。また、途中から、腕をもう少しだけ高く(目の高さまで)ふり上げたり、ひじが後ろに引かれるように意識したりと、動きに変化を加えてもよいです。
基本運動その3

- (1)基本姿勢で首や肩、腕をダラリと脱力して、息を吐きながらゆっくりと上体を前に倒します。
- (2)苦しくなる手前で止めて、一呼吸。
- (3)次に、体を戻していきます。先に顔を起こし、息を吐きながらゆっくりと、足裏で床を踏むようにして体を起こします。
- (4)立ちあがって一呼吸したら、続いて、腰に手を当てて体を安定させて、息を吐きながらゆっくりと上体を後ろに反らしていきます。
- (5)苦しくなる手前で止めて、一呼吸したら、息を吐きながらゆっくりと戻します。以上を3~5回。
基本運動その4
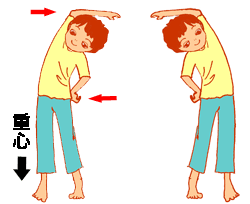
- (1)基本姿勢で片方の手を腰に当てて、息を吐きながら、ゆっくりと上体を横に倒していきます。
- (2)このとき、脇腹が伸びる側の足に重心をかけます。つまり、左に倒す時は右足に、右に倒す時は左足に重心がかかります。
- (3)また、重心のかからない側の足は、体を倒していくときにかかとが浮いてきます。
- (4)左右に倒す感覚を比べ、気持ちよく動く側へ3~5回倒しましょう。
基本運動その5
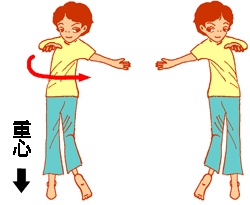
- (1)基本姿勢で、息を吐きながら、上体をゆっくりと左右にねじります。
- (2)右にねじるなら、右足に重心を移しながら上体をねじり、腕を段々と上げて、顔も目も、後ろを見るようにねじります。重心のかかる足裏は、ぴったりと床についたまま。反対の脚はかかとが浮いて来ます。
- (3)左右の差が感じ取れたら、ねじりにくい側から気持ちよく動く側へ、(2)の要領で息を吐きながらゆっくりとねじります。
- (4)違和感が生じる手前で止まって一呼吸おき、息を吐きながら、上体を戻します。3~5回。
基本運動その6

- (1)基本姿勢で、息を吐きながらゆっくりと、つま先立ちになりながら、両腕を体の前方から上げていきます。(指先も伸ばします。)
- (2)一方の腕が上がりにくいときは、同じ側の足に重心をかけると上がります。
- (3)体が伸びきったところでグラグラしないように一呼吸して、呼気で、かかとと両腕をバサッと一気に下ろします。3~5回。
- (4)また、両腕を上げるとき、体の前から上げるだけでなく、横から上げたり、斜め前から上げたりすると、重心のバランスが取れてきます。
体の歪みは足から
“四つ足の動物が二本足で立ったのが人間。”(『万病を治せる妙療法』より。)というわけで、操体では、足が土台であり、からだの歪みは足の歪みから始まると考えます。なので、肩や手の指の痛みをなんとかしたいとしても、歪みを修正するには足から始めます。足といっても、具体的には膝から始める(ことが多い)のですが、これは手助けの人がいたほうがうまくいくので、ひとりの操体法では、たとえ上半身の不調でも下半身の操体法をしっかりやるのだと、知っておいてください。
また、「基本の操体法」や「操体法の基本運動」の動きの中に、足やひざの修正も含まれています。動診の際に、つながりながら動く体のすみずみまで感覚を伸ばし、感じ取るようにしてみましょう。
*足に関する操体法は「足からの手当て」の項目に少し書きます!