医の自給自足
手からの手当て-1
手から始める
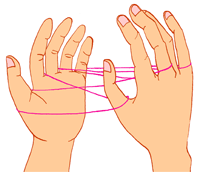 直立二足歩行をする以前、人類の祖先は4本の手を使って樹上に暮らしていたとされています。そのうちの2本が体重を支えて歩く役割りに変わり、枝をつかみ、体を支えることから解放された残りの2本は、感受性を高め、ずっと器用な動きをするようになりました。時に、足が人間の存在そのものの象徴であるように、手は探索や操作、創造のほかに意思表示や対話にも使われ、言葉にならない心境や感情を象徴します。一方、手にも足と似た健康法がさまざまにあります。
直立二足歩行をする以前、人類の祖先は4本の手を使って樹上に暮らしていたとされています。そのうちの2本が体重を支えて歩く役割りに変わり、枝をつかみ、体を支えることから解放された残りの2本は、感受性を高め、ずっと器用な動きをするようになりました。時に、足が人間の存在そのものの象徴であるように、手は探索や操作、創造のほかに意思表示や対話にも使われ、言葉にならない心境や感情を象徴します。一方、手にも足と似た健康法がさまざまにあります。
- (1)全身の体液の巡り、特に頭部の血液循環を促したり脳への良い刺激として、手の指を動かしたり手作業をすることを重視。
- (2)体の構造、特に上半身(上肢・頸部・頭部・胸郭)への連動を利用して、手の歪みや緊張を解消したり動きを回復させて全身に波及させる。
- (3)全身には力学的な情報を伝える筋膜のネットワークがあり、調整のしやすい手を利用する。
- (4)中医学でいう“気”の通り道の経絡が手も通過するとして、手の経穴(ツボ)を利用する
- (5)体の特定部位に対応する反応点やゾーンが手にある、もしくは全身の縮図が手に表れるとして、手の反応点や手の全体を利用する。また、形が似ている個所は相関関係がある、部分が全体を表す(自己相関性やフラクタル)といった考えから手の各部を利用する方法もあります。
- (6)全身に分布する神経の中で手の神経が最も敏感なことから、手に対する刺激を利用する。
実際には、どれかひとつを切り取った方法はなく、異なる次元を無意識に(もしくは意識して)同時にアプローチしているのでしょう。
操体法での考え方
操体法では、体の調整は土台の足から上へ調べ進めていくのが基本となるため、肩や腕、手指になんらかの問題があるときも足から始めます(*厳密には、肩の問題の中には、足に変化が出ているものと出ないものがあると、橋本先生の著書に書かれています)。手の問題がある場合は、操体法の基本の動きから始めてみてください!ここでは、手から全身の調和にはたらきかけるのを目的に、なるべくやりやすい動きをまとめてみました。手の動きが変わると、息詰まった空気が入れ替わるような気分の変化も起こります。
腕を動かす操体法
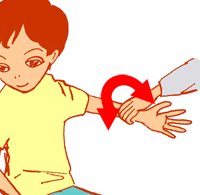
- (1)床に正座をするか椅子に腰かけて背を自然に伸ばし、腕は自然に下げてひざの上におきます。
- (2)肩甲骨の外側(脇の下の背中側)の筋肉を、手伝いの人がいたら摘まんでもらい、痛みを感じる個所を探ります。自分では、反対の手の親指を脇の下に当て、残りの指でこの水かきの筋肉をつまむように探します。
- (3)手伝いの人がいたら、特に痛みのあった側の手首を軽く押さえてもらい、腕を内側と外側に回して動診をします。
- (4)違和感を感じる手前で止めて、そこから反対の方向へ腕をねじり、3~5秒止めてから瞬間に脱力します。(肩から脱力出来ると尚良い。)
- (5)手伝いの人は、受け手が腕をねじるのをわずかに抵抗します。
- (6)(2)の痛みに変化があるか確かめてみましょう。
*動診をするときに、腕を上げ下げして脇の下の角度を変えてみると良いので、少し難しいですが試してみてください。ひとりで行うときは、なるべく手首を支持点にして、手首より上を連動させます。
両腕同時に操体法
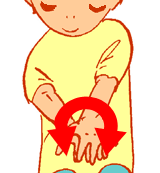
- (1)座った姿勢で、両腕を自然に伸ばして手のひらをゆるく合わせます。
- (2)手首を支持点に、合わせた手を内側/外側に回して動診をします。
- (3)動きやすい側にひねり、3~5秒止めて脱力します。
- (4)肩から先も自然に連動させましょう。
*日常で右手をよく使う場合、右腕が内側へ、左腕が外側へひねりやすい傾向があるため、この動きがうまく作用します。両腕が同じ側へひねりやすい場合、片腕ずつ行ってください。
仰向けで腕を動かす操体法

- (1)仰向けになり、手首をなるべく支持点にして、左右の腕を交互に内側と外側に回して動診をします。
- (2)どちらの腕も動かしやすい方へ、ゆっくりと同時に回します。
- (3)このとき、気持ちよく感じる位置に腕をずらしても良く(=脇をいくらか開ける)、全身を自然に連動させましょう。
- (4)3~5秒止めてから、瞬間に脱力します。
*仰向けになると手首の動きがやや少なくなりますが、布団の中でもできるため、就寝前や起床時に取り入れやすい動きです。
腕から手首の操体法
- (1)床に正座をしたり椅子に腰かけて、背中に無理のかからない高さの机や台に、緊張の強い側の腕のひじを置きます。
- (2)その姿勢で手首を反らす/曲げるの動診をします。ひじの角度は90度程度。
- (3)動かしやすい側に手首を動かしたまま、ひじを支持点にして、ひじの角度を変えずに腕を内/外に回して動診をします。
- (4)気持ちよく感じるところで3~5秒止めてから、脱力します。
*空いている手でわずかに抵抗をかけると効き目が増します。
- 1
- 2
- 3
- 4