医の自給自足
足からの手当て-1
足から始める
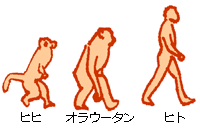 地球上に現存する150万種以上の動物の中で、直立で二足歩行をするのはヒト(ホモサピエンス/人間)だけ。直立二足歩行は人間の存在そのものの象徴となり、世界中のことわざや言語、哲学、芸術などさまざまな場面に登場し、一方、歩行や足に着目する健康法も多く、今も新しい発見が続いています。健康から足を見る観点を大まかに整理すると、以下のようになるでしょうか。
地球上に現存する150万種以上の動物の中で、直立で二足歩行をするのはヒト(ホモサピエンス/人間)だけ。直立二足歩行は人間の存在そのものの象徴となり、世界中のことわざや言語、哲学、芸術などさまざまな場面に登場し、一方、歩行や足に着目する健康法も多く、今も新しい発見が続いています。健康から足を見る観点を大まかに整理すると、以下のようになるでしょうか。
- (1)全身の体液(血液やリンパ)の巡りは足が支えるとして、足を動かしたり、歩くことを重視。
- (2)体の構造の土台は足であり、全身は連動するとして、足の歪みや緊張を解消して動きを回復し、全身の運動系や機能に波及させる。
- (3)全身には力学的な情報を伝える筋膜のネットワークがあり、調整のしやすい足を利用する。
- (4)中医学でいう“気”の通り道の経絡が足も通過するとして、足の経穴(ツボ)を利用する。
- (5)体の特定部位に対応する反応点やゾーンが足にある、もしくは全身の縮図が足に表れるとし、足の反応点や足部全体を利用する。また、形が似ている個所は相関関係がある、部分が全体を表す(自己相関性やフラクタル)といった考えから、足の各部を利用する方法もあります。
実際には、どれかひとつを切り取った方法はなく、異なる次元を無意識に(もしくは意識して)同時にアプローチしていると思います。
足を動かす操体法!
足を土台と考える操体法の基本の動きには、足を動かして連動させるものがいくつかあります。足を操作しただけで、腰痛や肩こりが楽になったり頭がすっきりしたり、立ち方や歩き方が変わったり、重心が落ち着いたり、広範囲に影響します。ふたりで行うと効き目が表れやすい操体法なので、誰か、できれば少し慣れた人に手伝ってもらうといいですね。
「ひかがみ(ひざの裏)の緊張をとる」

- (1)受け手は仰向けに寝て力を抜き、ひざ頭が軽く触れるようにして膝を(約90度に)立てます。
- (2)手伝いの人はひざ裏に指を当て、圧痛点を探ります。
- (3)両手を受け手の足の甲に置き、圧痛点のある側に軽く(垂直方向に)抵抗を与え、指先を上げさせます。
- (4)受け手は、(抵抗を受けながら)かかとを支持点として徐々に反らし、足指も反らします。
- (5)手伝いの人は、受け手の足が上がり切ったところで3~5秒止めて、瞬間脱力させます。
- (6)2~3回繰り返すと圧痛点はほぼ消えています。圧痛点が両側にあるときは、片側ずつ行います。
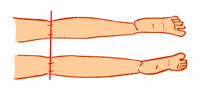 *上で変化がない場合、ひざをもう少し深く曲げてみてください。
*上で変化がない場合、ひざをもう少し深く曲げてみてください。
*圧痛点(シコリ)は、ひざを曲げた状態で指を回し入れ、ひざ裏の柔らかく凹んだ部分で、ちょうど折り曲げてできた横のライン上を、少し押すようにして滑らせて探します。
ひとりで行うときは、かかとを支持点に足をグッと反らして3~5秒保ち→瞬間脱力、を3~5回です。
「うつ伏せのかかと回し」
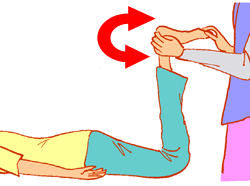
- (1)受け手はうつ伏せになって力を抜き、ひざ頭は揃え、ひざとかかとを直角に曲げます。
- (2)手伝いの人は、受け手のかかとを軸にして、指先を左右に回して動診をします。
- (3)両手で左右同時にかかとと指先を支え、軽く抵抗を与えつつ、動きやすい方向にゆっくりと回旋させます。
- (4)どこかに緊張が生じる手前で2~3秒止めて瞬間脱力。
- (5)2~3回繰り返します。
*かかとではなく、指先を軸に回すと連動する個所が変わります。
「足首の操体法」
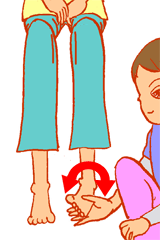
- (1)足から力が抜けるように、足が地面に届かずブラブラする高さの椅子や台に深く腰かけます。
- (2)手伝いの人は、受け手の足を軽くつかみ、足裏を内側/外側にひねって動診をします。
- (3)受け手は気持ちよく動く側にひねり、手伝いの人は軽く抵抗します。
- (4)緊張が生じる手前で2~3秒止めて、瞬間脱力します。
- (5)同様に、かかとを支持点にして指先を内側/外側に回す動き、また、かかとを支持点にして指先を上下の動き(足首を曲げる/伸ばす)も行います。(5)では、手伝いの人は片手で指先だけをつかむ、もしくは、片手でかかとを支えてもう片方の手で指先をつかみます。
*ひとりでの足首の操体法は3ページ目をご覧ください!
足指の操体法
これは足指の間の痛みを探り、痛みから逃げるという操体法のやり方のひとつを使います。熟練した術者の最高のテクニックが必要とされ、橋本先生もその著書には、“指までやらねばならないことは滅多にない”と書かれています。また、『操体法/橋本敬三の世界(2005年/NHKエンタープライズ発行)』の映像の中には、ご自身の足の捻挫を題材に、足の親指を中趾骨関節から動かして、瞬間脱力で調整する橋本先生の姿を見ることができますので、ご興味のある方はご参照ください。
それとは別に、操体法には足指から体をゆらしたり足を落とすという方法がありまして、こちらは少し練習すれば誰にでもできます。応用が進んでいるためか共通の呼び名はないようで、私が教えていただいた先生は「あしゆら」と名付けられていました。ただ、ひとりではできないため、別の機会にご紹介したいと思います!